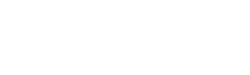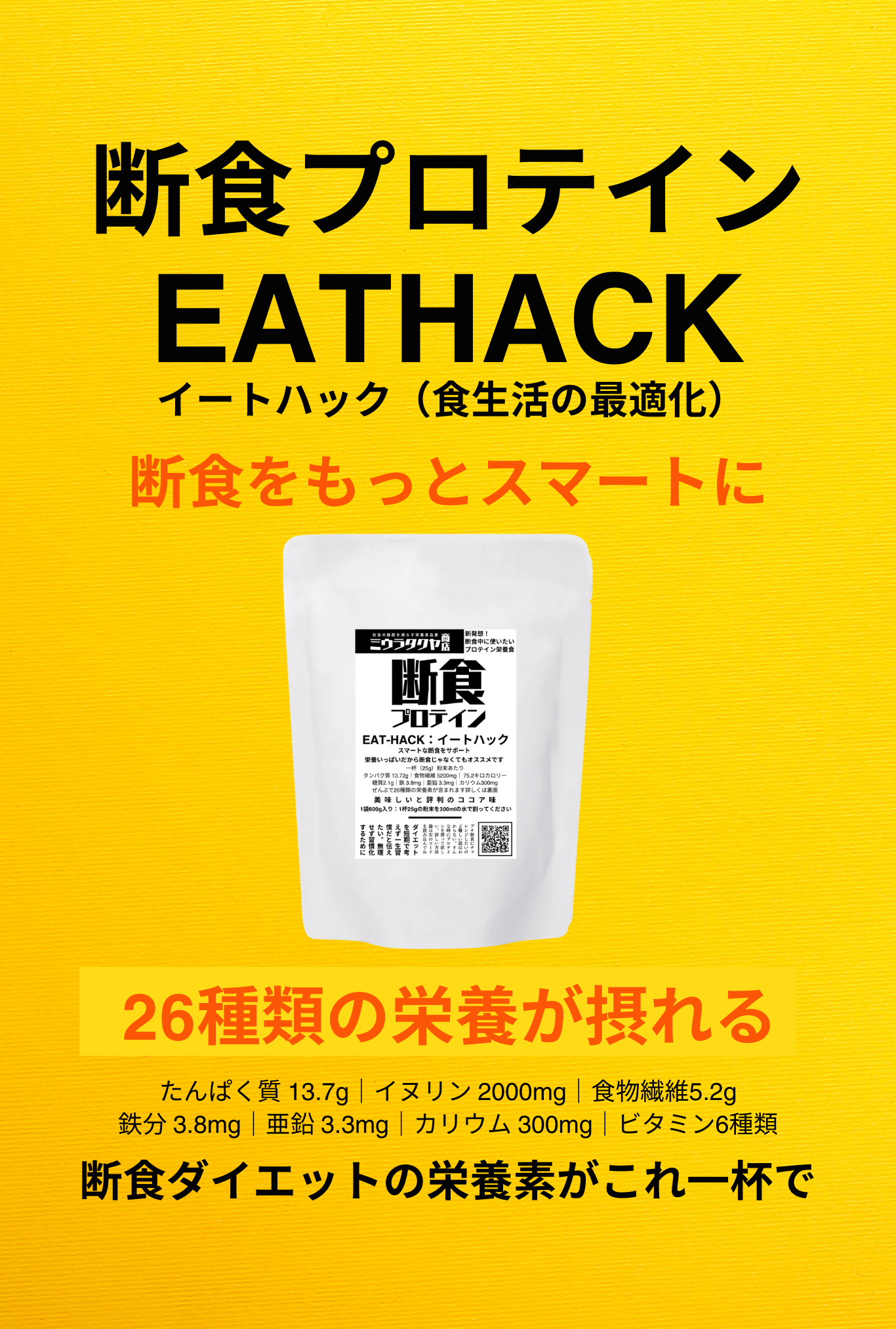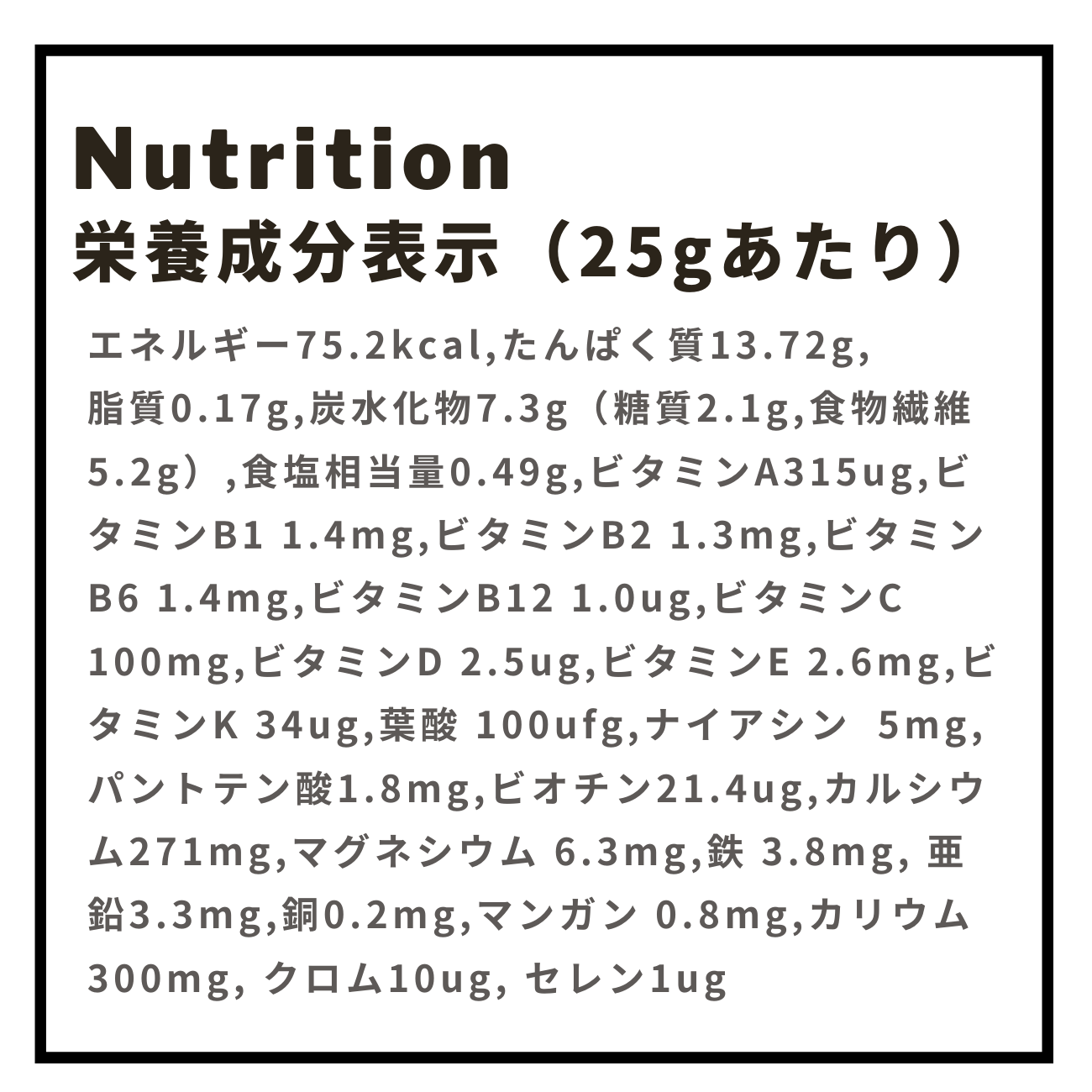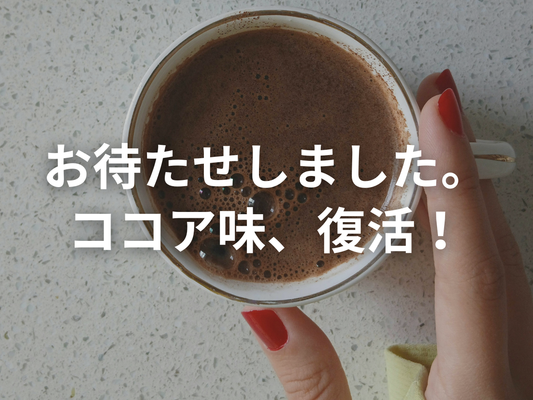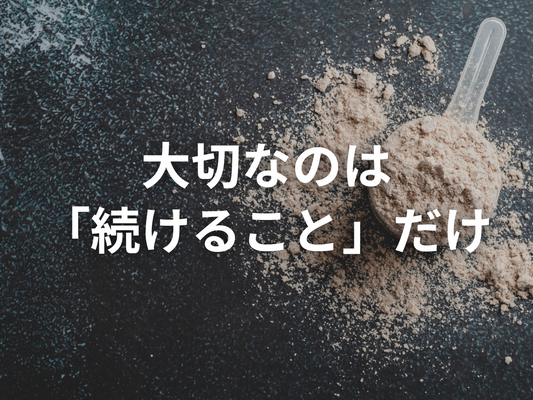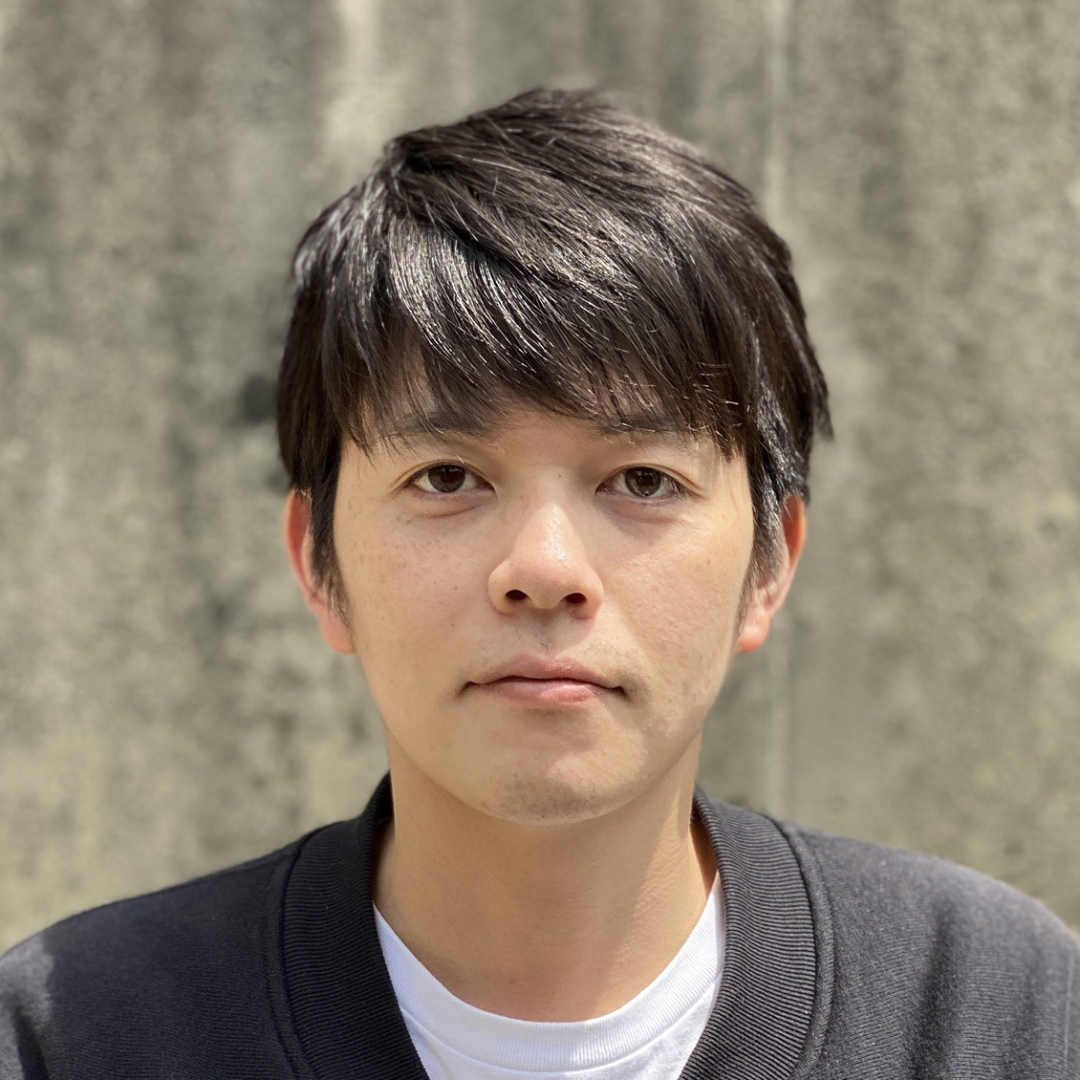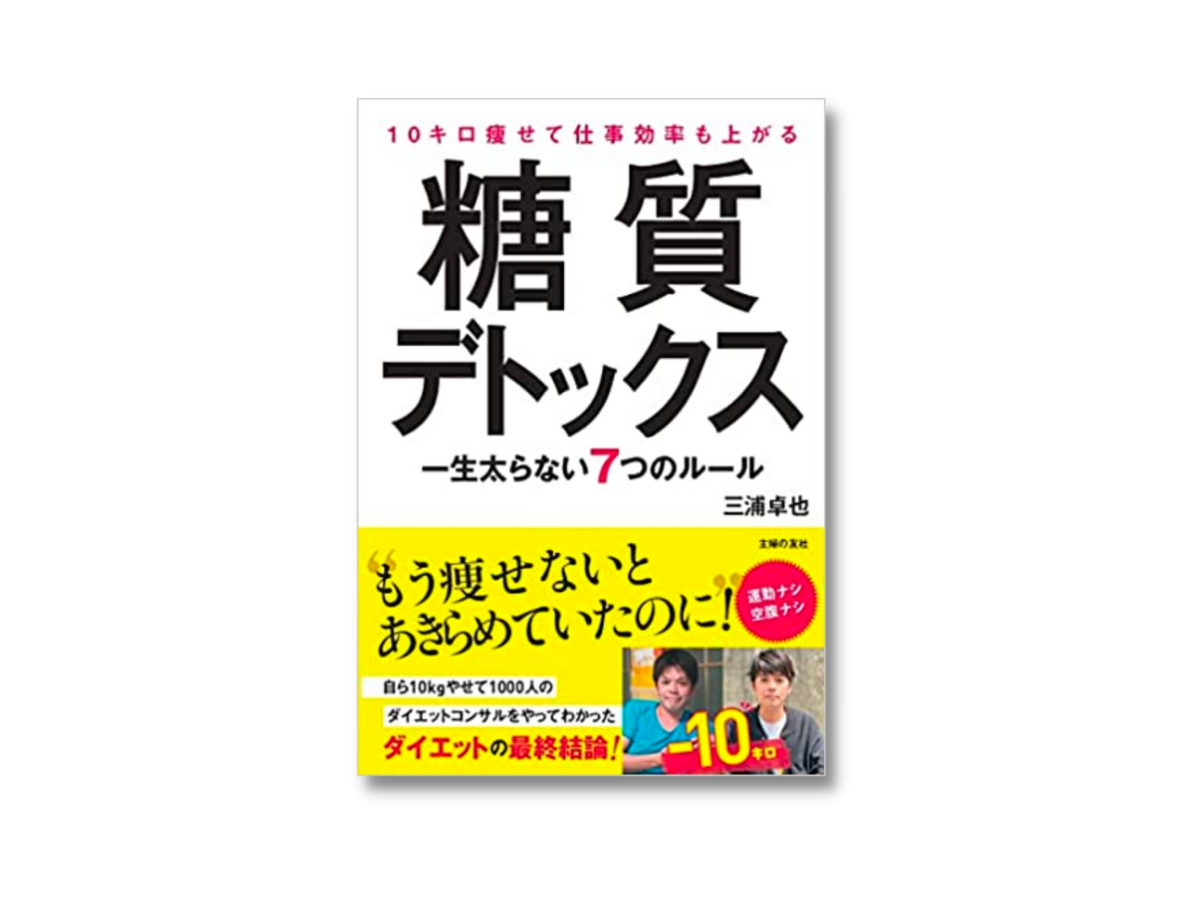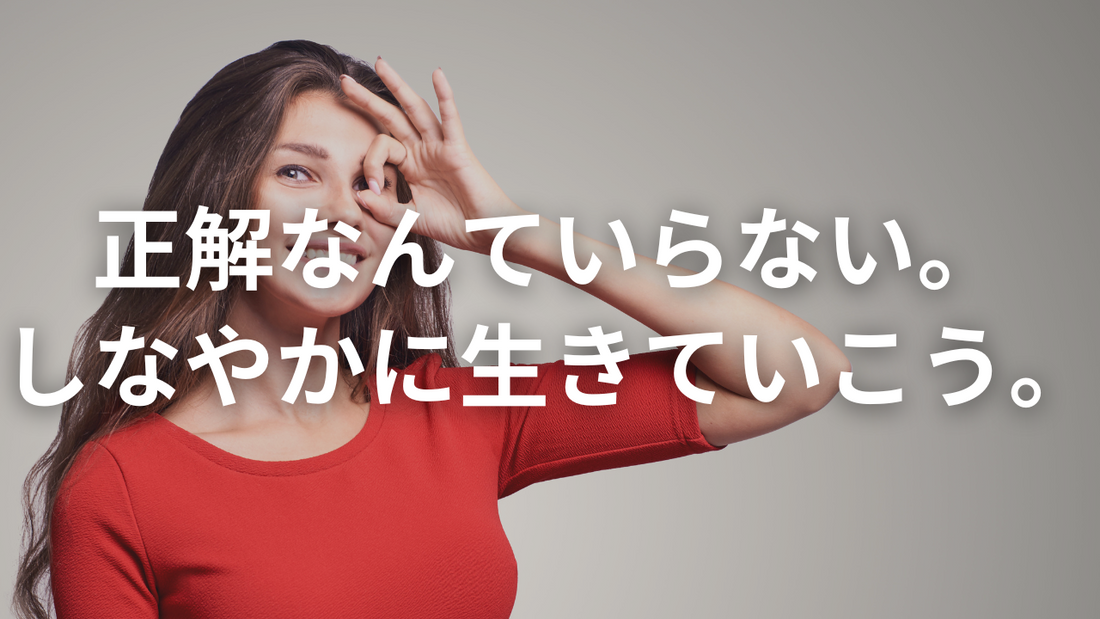
人はなぜ白黒つけたがるのか? それでも“グレー”を受け入れて生きるという選択
「白か黒か」で生きるのは、実はとても楽なこと
人と話しているとよく思う。
「この人、やたらと白黒をつけたがるな」と。
たとえば、
「それって結局いいの?悪いの?」
「やるなら100%じゃないと意味ないじゃん」
「成功か、失敗か。それ以外に何があるの?」
そんなふうに、物事を「正解/不正解」「勝ち/負け」「成功/失敗」みたいに二択で語りたがる人はとても多い。
でもその感覚、実は人間の本能とも言えるんです。
心理学的にも宗教的にも「白黒思考」は自然なこと
僕たちの脳は、複雑な情報を単純化して理解するようにできている。
判断を速く、エネルギーを使わずに下すためには、「これは正しい、あれは間違い」と瞬時に結論を出す回路が必要だった。
心理学的にはこの思考は「全か無か思考(All-or-Nothing Thinking)」と呼ばれ、うつや不安の一因とも言われています(A. T. ベック『認知療法の理論と実際』)。
また、宗教的にも、善と悪、聖と俗、神と悪魔など、明快な二元論で世界を秩序づける構造が古代から使われてきました(エリアーデ『聖と俗』など)。
つまり、「白黒つけたがる」って、ある意味、僕たちが安心して生きるための仕組みでもあるんです。
でも――人生のほとんどはグレーでできている
だけど。
本当に大切なことって、「白でも黒でもない世界」にあるんじゃないかと、僕は思ってる。
たとえば――
・誰かとの人間関係、簡単に善悪では割り切れない
・自分のキャリアの選択、どっちを選んでも「正解」にはならないかもしれない
・ダイエットの方法も、子育ても、経営も、「これが正解です」なんてことはない
むしろ、「うまくいってるかも」と思ったら、別の問題が見えてくる。
「失敗したかも」と思ったら、そこから学びがあったと気づく。
そんな白黒じゃ測れない、矛盾や曖昧さに満ちた現実こそが、“生きている”ということなんじゃないかと思う。
じゃあ、どう生きればいいのか?
僕は、白黒つけたくなる衝動を責めたいわけじゃない。
ただ、「それしか見えなくなってしまうと、かえって不幸になってしまう」ということを言いたい。
だから、“思考のスタンス”を変えてみる。
それだけで、世界の見え方が少しずつ変わってくる。
① 「結論を急がない」姿勢を持つ
わからないことは、わからないままにしておく。
白黒つけずに、“保留”する。
「この人ってどういう人だろう?」
「この選択、今はまだ評価できないけど、自分にとって意味があるかもしれない」
そんなふうに、“待てる”ことが成熟した思考だと思っています。
② 「正しさより、やさしさ」
相手の間違いを正したくなるときこそ、自分に問う。
「この正論は、相手を救うだろうか?」
人は正論では動かない。
正しいかより、“伝え方”と“タイミング”の方が大事だったりする。
やさしさには、力があります。
③ 「矛盾を許す力」を育てる
自分の中にも、人の中にも、たくさんの矛盾がある。
・前向きな自分もいれば、ネガティブな自分もいる
・優しくありたいと思いながら、イライラしてしまうこともある
・諦めたいのに、どこかでまだ期待している自分もいる
そういう矛盾を、“ダメなこと”と切り捨てないで抱えて生きる。
それって、すごく強いことだと思う。
④ 「問い続けること」が豊かさを生む
「どっちが正しいか」ではなく、
「自分にとって意味があるのはどっちか?」と問い続ける。
結論を出すことがゴールじゃなくて、
問いを持ち続けることこそが、人を深くしてくれる。
⑤ 「100点じゃなくても、生きててOK」
完璧じゃないとダメ、じゃなくて、
「60点でも立派」「今日も生きてるだけでOK」。
そんな自己肯定感で生きられたら、
もっと人に優しくなれる。
もっとチャレンジできる。
もっと毎日が愛おしくなる。
グレーの中で生きる、それが成熟した人生だと思う
何かを決めつけず、矛盾を抱えながら、問いを持ち続けて生きていく。
それはちょっと面倒くさい生き方かもしれない。
でも、僕はそういう人が、一番「しなやかで、幸せ」に見える。
まとめ:白黒じゃない世界を生きる覚悟
人間には、白黒をつけたがる本能があります。
でもそれに気づいた上で、「あえてグレーを生きる」という選択をする。
・自分の判断を保留にできる人
・他者の矛盾を許せる人
・不完全なまま進み続ける人
そういう人が増えたら、世界はもっとやさしくなると思います。
そして、そういう思考こそが、自分自身を“幸せにするための土台”になるんじゃないでしょうか。
書き手:三浦卓也
ダイエットの相談も人生の相談も受けてます(笑)
話したくなったらLINEでどうぞ → https://lin.ee/Bj36rez