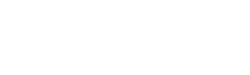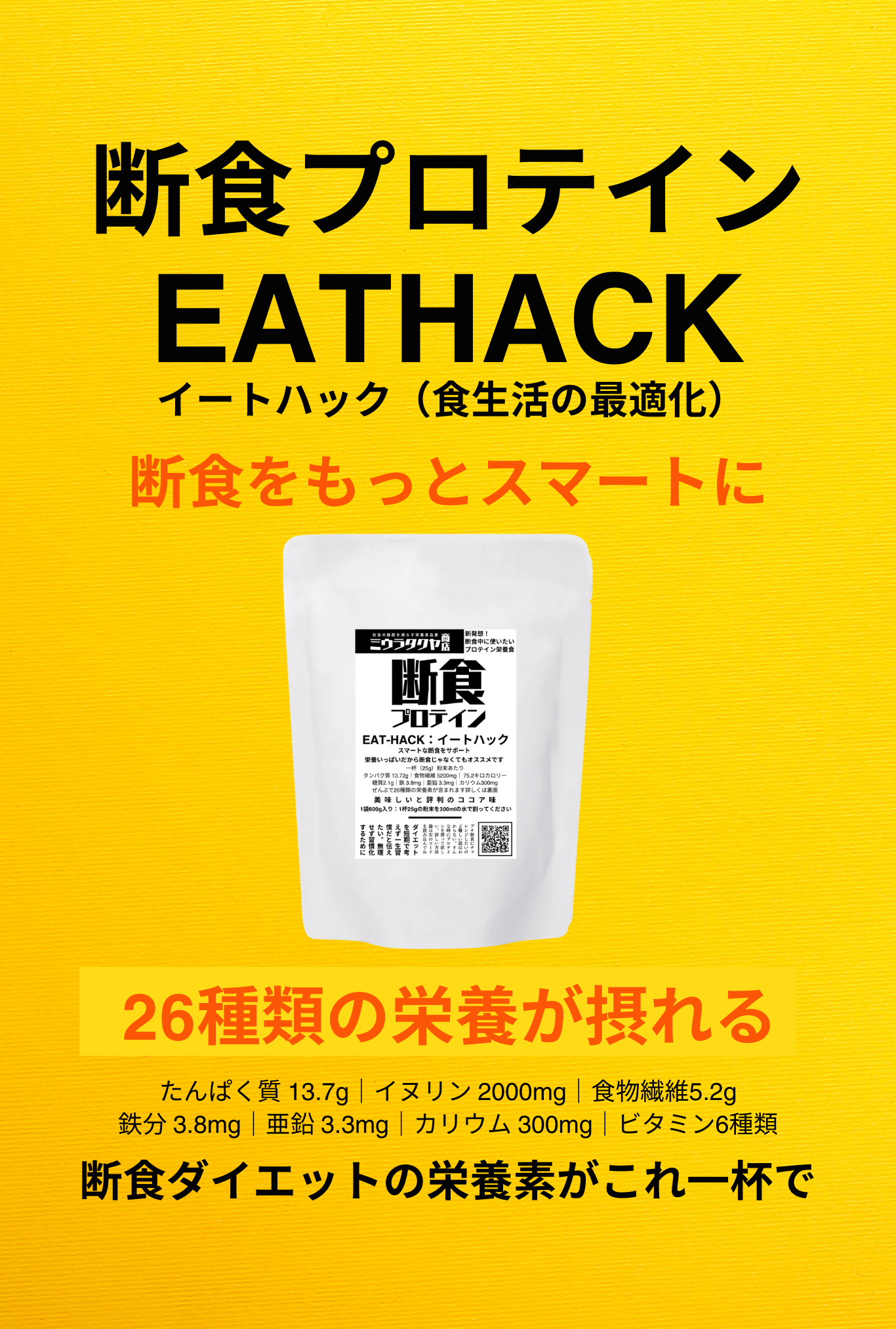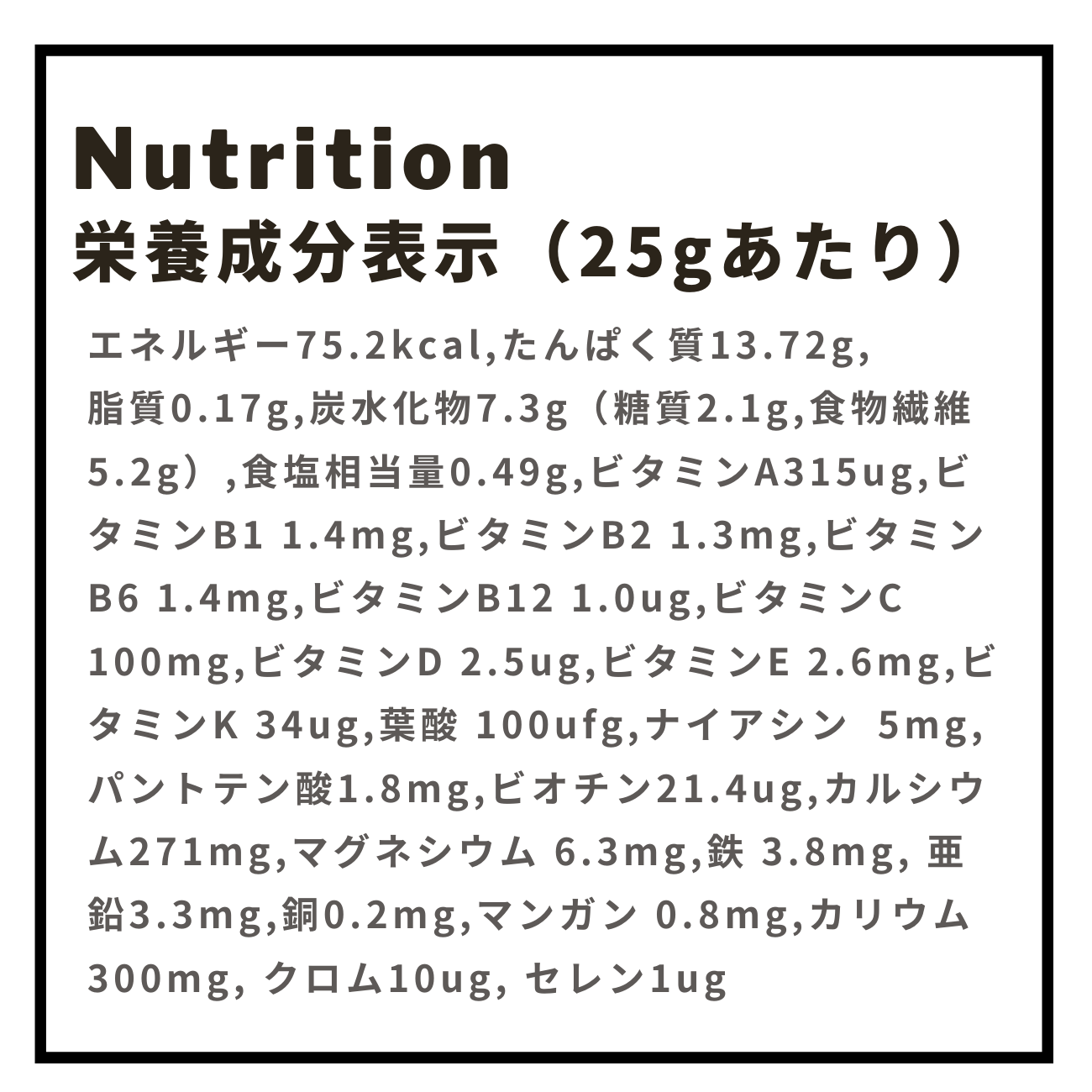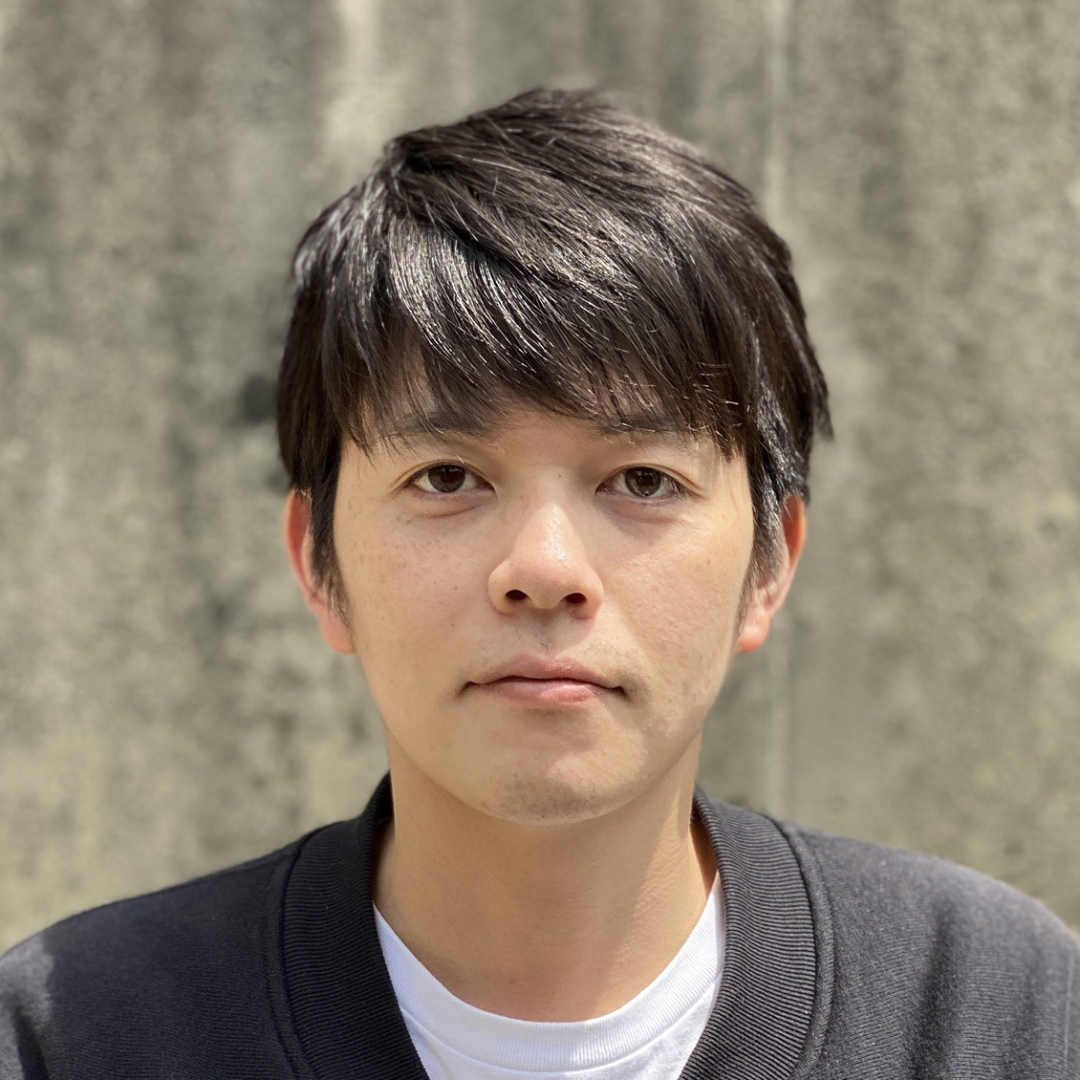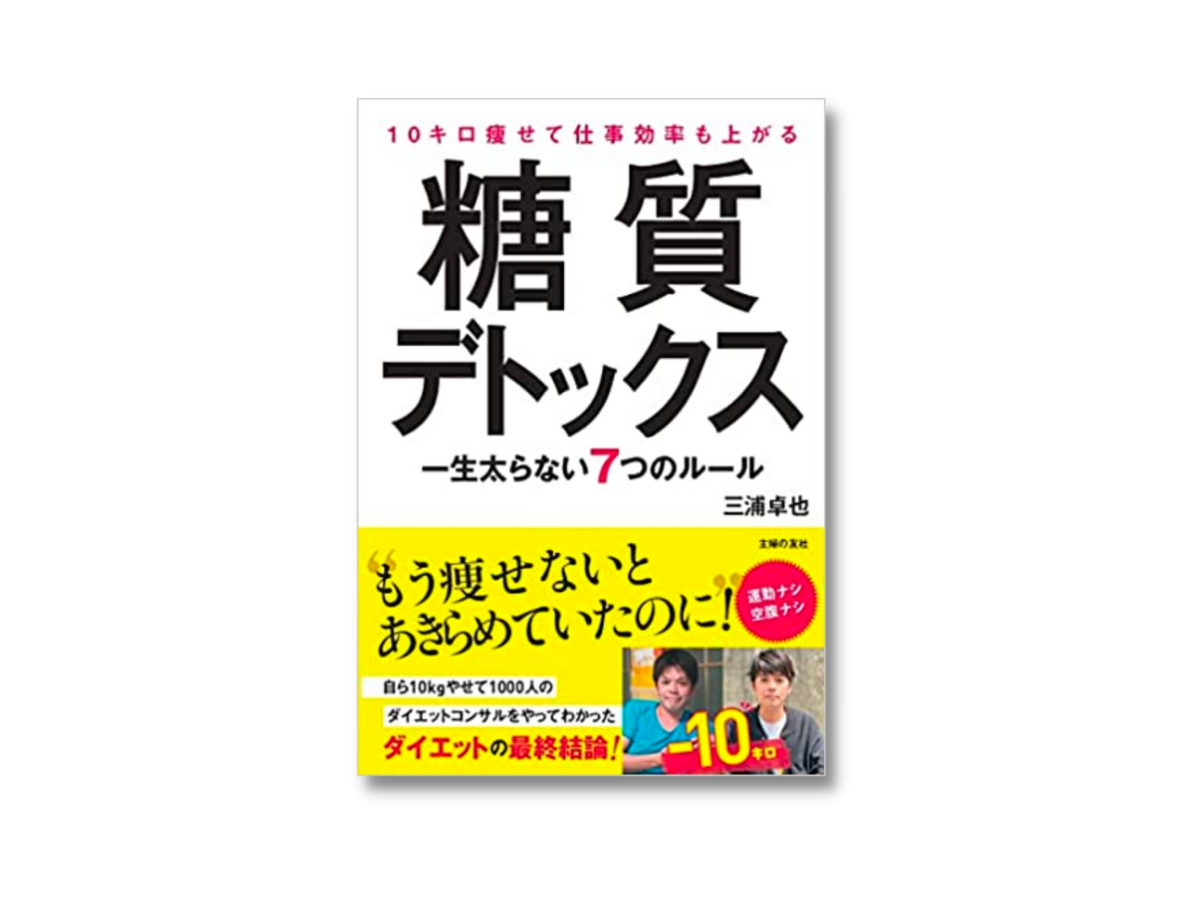ダイエットと科学とエビデンスの関係性(最新版)
こんにちは、最近 “ダイエット情報が多すぎて逆に食欲失せるわ…” と感じる三浦卓也です。
(情報だけで満腹になるのは、世界で唯一ダイエッターくらいです。)
今日は「エビデンス」「科学」「ダイエット」の関係について、かなり本質的な話をします。
エビデンスとは「データそのもの」
エビデンス(evidence)とは、研究データ・観測結果・統計など、揺るがない事実を指します。
シンプルに言えば、位置情報のような“客観的な点”です。
ここには解釈は入りません。
私たちが受け取る情報は「エビデンスではなく、誰かの解釈」
世の中に出回っている「エビデンスに基づく〇〇」は、
実際には エビデンスそのものではなく“誰かの解釈” です。
同じ研究でも、
・どこを切り取るか
・どこを強調するか
・どの文脈で語るか
・どんな立場の人が発信するか
これらで“見え方”は大きく変わります。
Aさん「糖質制限はメリットが大きい」
Bさん「糖質制限にはリスクがある」
同じデータでも結論が逆転するのは珍しくありません。
データから“傾向”を読み取ることはできる
ただし誤解しないでほしいのは、
解釈が違うだけで、データから読み取れる“傾向”は確かに存在する
ということです。
例えば、特定の栄養素の摂取と体脂肪の変動に関するデータがあれば、
「多くの人ではこういう傾向がある」という方向性は読み取れます。
つまり、解釈が違っても
データから得られる“方向性”自体は崩れない。
しかし問題はここから。
1つのエビデンスで“主張”してはいけない
本来、「主張」というのは
・複数のエビデンス
・データの積み上げ
・学術的な整合性
・思考の一貫性
・文脈の理解
これらが揃って初めて成り立つものです。
にもかかわらず世の中には、
“1つのエビデンスだけ”を持ち出して
自分の主張を強く印象づけるために語る人
がいます。
これは本質的ではありません。
エビデンスは点であり、
主張は点と点をつなぎ合わせた線で語られるべきもの。
1本の論文だけで
「これは危険」
「これは正しい」
と断定するのは、学術的にも健康情報としても非常に危険です。
科学は“平均の話”であり、個体差までは語れない
科学が示すのは「多くの人に当てはまる傾向」です。
しかしダイエットは、
・遺伝
・生活習慣
・自律神経
・ストレス
・睡眠
・ホルモン
・胃腸の強さ
これらの変数が複雑に絡む世界です。
家族でさえ体質が違うように、
同じ食事方法が全員に当てはまるとは限りません。
だから、「平均の話」がそのまま「あなた個人の話」になるわけではない。
解釈に振り回されず、本質に近づくためには“知識の積み重ね”が必要
エビデンスは事実。
しかし、私たちに届くのは解釈。
さらに主張には複数の根拠が必要。
これらを理解するには、
受け手側の知識の土台が不可欠です。
代謝、栄養、睡眠、ストレス管理。
これらの基礎を理解していれば、
・この情報は極端ではないか
・この人の主張はどんな根拠の積み上げか
・どこに“解釈”が入っているか
を見抜けるようになります。
一緒に「情報に振り回されない力」をつけましょう
10年以上ダイエットを学んできて、
知識があるだけで人生が本当に楽になると実感しています。
だから僕はこれからも、
ブログやYouTubeで本質的な情報を発信し続けます。
YouTubeはこちら:
https://www.youtube.com/channel/UCduZwSU2PQs-hnZFRtgSbBw
一緒に「本質的な理解」を積み重ねていきましょう。